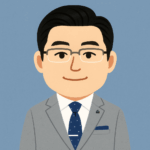従業員に決算書開示を求められたら?経営者と従業員の本音と実務対応

「うちの会社、決算ってどうなってるんですか?」
経理や管理部門の方なら、一度は従業員にこう聞かれたことがあるのではないでしょうか。
特に中小企業では、決算書は経営者とごく一部の人しか見られない”ブラックボックス”となっています。
従業員から「決算書を見せて欲しい」と言われたとき、経営者・経理担当者としてどのように対応すべきかを整理してみます。
中小企業の決算書は開示しなければならないのか?
株式会社の場合、「会社法」においてその規模に関係なく「決算公告」を行うことが義務*となっています。
*注:決算公告義務(会社法440条)、株主・債権者への開示義務(会社法第442条)
しかし、そのことを知らない経営者も多く、実際にはほとんどの会社が決算公告を行っていないので、この義務は形骸化しています。
中小企業が決算広告しない理由としては、費用がかかるだけでメリットがほとんどないといったところでしょうか。「株主」や「債権者」からの開示請求があった場合は開示しなければなりませんが、「従業員」が決算書の開示を求めたとしても、法的には開示請求権を持っていないので経営者の判断で断ることができます。
経営者からすれば、決算書には会社の内情を知るうえでのセンシティブな情報も載っていますので、開示には当然慎重になります。
経理担当者も業務上で知り得た内容を許可なく開示すると懲戒処分の対象となる可能性がありますので気をつけましょう。
決算書を開示するメリット・デメリット
私個人は決算書の数字を広く従業員と共有して経営課題を共有しながら仕事をしたいと考えています。
経営者から根拠や裏付けとともに方針説明を受けたほうが、会社からTOPダウンの目標をただこなすだけよりも能動的に動けると考えるからです。
しかし、経営者は決算書の内容理解もそこそこに、黒字だったら給料を上げろ、赤字であれば会社が危ないと言い、役員報酬も知られたくないから開示したくないと思っていたりします。
それなのに、このように思っている経営者ほど従業員に対して「経営者目線」を求めたりします。
オーナー経営者と従業員の間には経営に対して埋めがたい感覚の違いが存在しているのではないでしょうか。
大切なのは「なぜ開示を求めてきたのか?」という背景です。多くの場合は「不信感」「昇給への疑問」「会社の将来性」などが動機なので、単に断るよりもどんな数字なら共有できるかを考えましょう。
決算書を見せる前にやるべき「数字の共有」

それではどうすればこの現実と理想のギャップを埋めていけるのでしょうか。
結論としては、経営者と社員が共有すべき数字を本当に大事なものに絞ることです。
よくKPI(Key Performance Indicator)と言われたりしているものがそうです。
自社のKPIを共有することで、会社、部門、従業員の目標を明らかにすることが大切だと思います。
決算書を開示して、その分析結果を従業員に説明しても、正直ピンとこない人のほうが多いと思います。
だからといって数字を一切公表しないのは、従業員を疑心暗鬼にしてしまいます。
かつて、外部コンサルタントからの指示で現場の負荷が上がった後、結果として「会社はあれで儲かったのだから、これくらいのこと聞いてくれてもいいだろ」と言ってきた従業員がいました。
正直、そんな感覚の従業員がいることに驚きましたが、数字をクローズにしていることとこの発言に多少の因果関係はあるだろうなと感じました。
決算書の開示より大切なのは「計数感覚の共有」
経営者にとっても従業員にとっても、一番大切なのは会社を発展継続させていくことだと思います。
そのためには、経営の成績である決算書を見て分析することも大事ですが、赤字にならないように自分自身の計数感覚(売上-費用=利益)を磨くことだと思います。
このことは、「つぶれない会社のリアルな経営経理戦略」(ブックレビューはこちら)でも述べられています。
自分自身の計数感覚にずれがないかどうかを、KPIや経営指標などで確認することで、常に軌道修正しながら次の手を考えることは、経営者にとっても従業員にとっても重要なスキルだと思います。
決算書を開示するかどうかは最終的には経営者の判断ですが、数字を共有しないまま「経営者目線」を要求しても伝わらないでしょう。
KPIなどを通じで「同じものさし」で会話できる組織こそ、本当の意味で強い組織となれるのではないでしょうか。